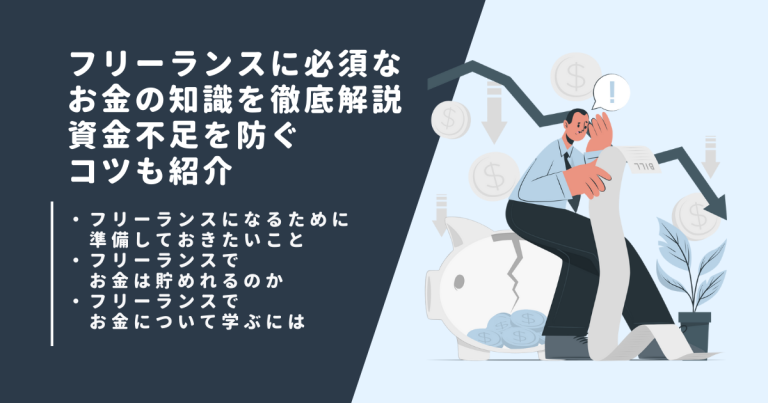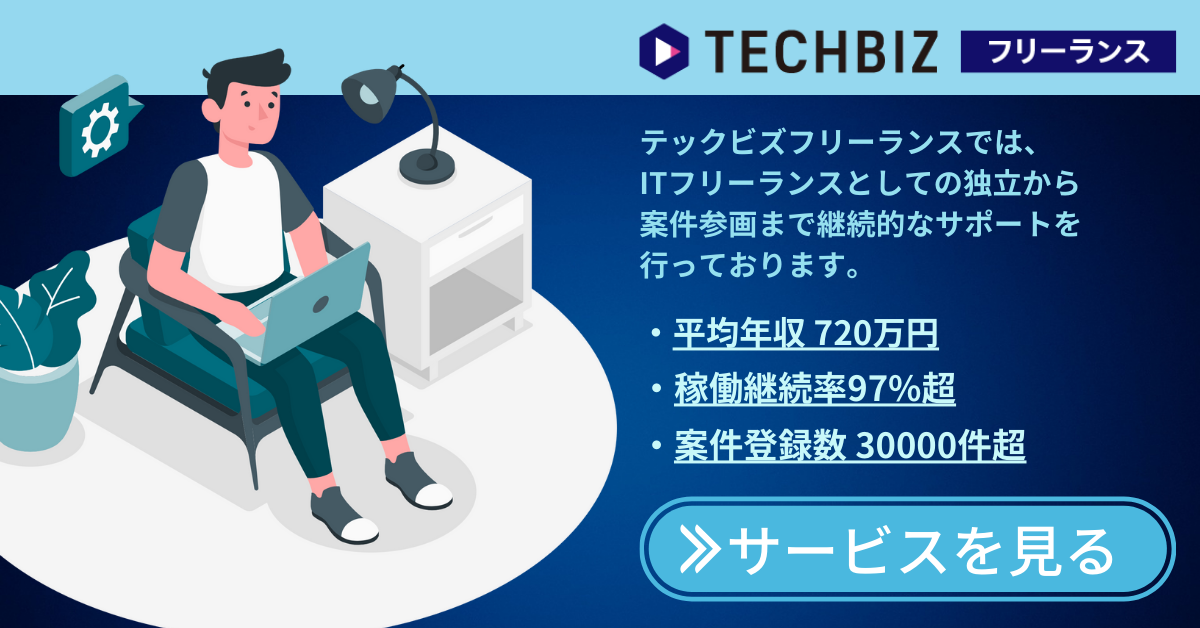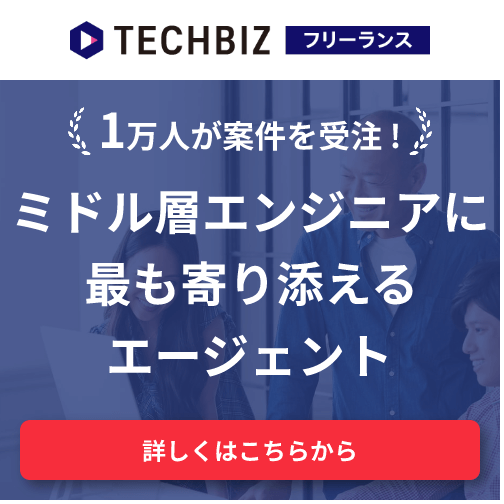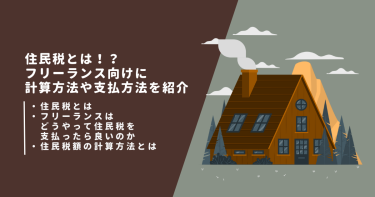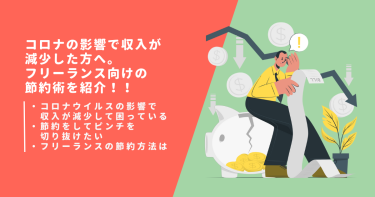・フリーランスでお金は貯められるのか
・フリーランスでお金について学ぶには
フリーランスへの道を模索している方々が、しばしば抱える不安の一つが経済面でしょう。会社員のように一定の給与が保証されなくなること、また税金の処理を全て自分で担う必要があることなど、お金にまつわる事項は頭を悩ませる要素となります。特に、お金の管理に関する知識がないままフリーランスに踏み出してしまうと、困難に直面したり、損失を被ったりする可能性が高まるでしょう。
そこで今回は、フリーランスを目指す方々が把握しておくべき金融の基本知識や、フリーランスとして安定した収入を確保し貯蓄を増やすテクニックについて解説していきます。
フリーランスに転身しても経済的な問題に直面しないよう、共に学んでいきましょう。
フリーランスになる前に準備しておきたいお金のこと
フリーランスになる前に準備しておきたいお金のことをお伝えしていきます。
①必要な収入と支出を把握しておく
②貯金を半年〜1年間生活できるぐらいしておく
③保険や年金に関する知識をある程度身につけておく
④確定申告に関する知識をある程度身につけておく
①必要な収入と支出を把握しておく
自身の生活を維持するために必要な収入と支出を理解し、把握しておくことは大切です。それをしっかりと把握していないと、生活を支えるために必要な仕事量がわからず、ただ闇雲に働き続けることになってしまいます。仕事の量を見積もれないと、新たな仕事を探しに行くべきタイミングも見極められません。
収入と支出をしっかりと理解することで、仕事の量を適切に調整することが可能となり、フリーランスとしてもよりスムーズに働くことが可能となるでしょう。
す。
②貯金を半年〜1年間生活できるぐらいしておく
収入と支出をしっかりと理解した上で、余剰分は貯蓄に回し、半年から1年間の生活費が賄える程度の金額を貯めておくことを推奨します。例えば、月々の生活費が20万円必要な方は、120万円から240万円程度を貯金として確保しておけば安心でしょう。
フリーランスとして独立したとしても、すぐに生活費を賄う収入を得られる保証はありません。また、一度得た仕事がずっと続くとは限りません。そのため、万が一の状況に備えて貯金をしておくことが重要です。フリーランスは収入が不安定であることが多いので、仕事が安定してきたと感じたとしても、一定の額を貯蓄に回すように心がけましょう。
フリーランスは失業保険が受けられない
フリーランスは失業保険を受け取ることができません。もし会社を辞めてフリーランスを目指す場合でも、失業保険を受け取るためには一定の就職活動を続けることが必要です。フリーランスとして仕事を得た時点で、失業保険の受給資格は失われます。また、フリーランスとして活動していながら失業保険を受けてしまうと、それは不正受給とみなされ、受給した金額を全額返還しなければならない場合もありますので、十分注意しましょう。
③保険や年金に関する知識をある程度身につけておく
保険や年金についての知識を一定程度身につけておくことが大切です。会社員の時は、これらの手続きの大部分が会社によって行われていたでしょう。しかし、個人事業主になると、これらの手続きは全て自分で行う必要があり、適切な手続きを行わないと脱税となってしまいます。また、開業後になってからこれらの事項を慌てて調べたり、手続きを行ったりすると、大変忙しくなります。
そのため、開業前からある程度事前に調査しておき、余裕を持って開業を進められるようにしましょう。
独立したての際は国民健康保険や住民税に注意
フリーランスになると、国民健康保険や住民税は自分で納める必要があります。これらを適切に支払えるように、国民健康保険や住民税分の資金はあらかじめ確保しておくようにしましょう。
特に会社員からフリーランスに転職した場合は注意が必要です。なぜなら、国民健康保険や住民税の額は前年度の所得に基づいて決まるため、会社員時代の収入が影響を及ぼします。フリーランスになりたてで収入がまだ少ない場合でも、予想以上に高額な税金が請求されることがあります。特に会社員時代には給与から自動的に天引きされていたため、意識せずにいた方は、過去の給与明細を確認してみることをおすすめします。
国民健康保険や国民年金以外の保険、年金も視野に入れておこう
フリーランスは基本的に国民健康保険や国民年金に加入しますが、これら以外の保険や年金についても視野に入れておくことが重要です。フリーランスが加入可能な保険や年金については、以下のようなものが存在します。
・国民年金基金
・確定拠出年金
・etc……
国民健康保険組合とは、同じ業種の人々が集まって組織する組合のことを指します。業種によりさまざまな組合が存在しますが、国民健康保険とは異なり、所得が増えても保険料が一定となることが多いです。そのため、収入が多い方にとっては有益な保険と言えます。
国民年金基金は、国民年金の加入者を対象とした年金基金です。これまでの国民年金を満額で支払っている方だけが、この基金に加入できます。
確定拠出年金は、金融資産の運用結果に基づいて年金額が決まる年金制度です。運用の成果には変動がありますが、掛け金以上の年金受給額が得られる可能性もあります。
他にも多種多様な保険や年金制度が存在しますので、独立する前にこれらについて調査しておくことをお勧めします。
④確定申告に関する知識をある程度身につけておく
フリーランスは確定申告も自分でする必要があるため、独立前にある程度知識を身につけておくようにしましょう。確定申告とは、以下のような税金の1年間の納税額を決めるために行う処理のことです。
・所得税
・住民税 etc…
毎年2月から3月に行われる確定申告のためには、日々の所得や経費の記録が必要不可欠となります。また、帳簿や領収書といった保存が必要な書類も多数存在します。
フリーランスとして活動する前に、このような要素を理解し、準備をしておくことが大切です。事前の準備を行うことで、記録の漏れや保存忘れを防ぐことができ、確定申告をスムーズに進められます。
確定申告を簡単に行うためのアプリについては、以下の記事で詳しく紹介していますので、ぜひご参照ください。
①収入を上げる
②先取り貯金をする
③節税をする
④資産運用を始める
①収入を上げる
自明のことかもしれませんが、フリーランスとして資産を増やしたいのであれば、まずは収入を増加させることを考慮すべきです。フリーランスは会社員とは異なり、自身の収入を自由に調節できます。
仕事量を増やす、または報酬を増加させる等、収入を増やすことで、それに応じて貯金も増えていくでしょう。しかし、仕事量を増やす、または報酬を増加させるためには、効率的に仕事を行う技術を学ぶ、あるいは自身のスキルを磨く等、自己投資も必要となります。
長期的な視野で、より多くの貯金をするためには、働き方やお金の使い方も見直すことが重要です。
②先取り貯金をする
フリーランスに限らず、貯金を増やしたい人におすすめの方法は、「先取り貯金」です。先取り貯金とは、収入を得た時点でその一部を先に貯金するというお金の管理方法です。
通常、貯金というと、生活費などの支出を行った後の余ったお金を貯金する、というイメージを持つかもしれません。しかし、その方法だとなかなか貯金が増えていきません。「毎月〇〇円は貯金する」と決めておき、その金額を収入があったらすぐに貯金に回すことで、毎月確実に貯金を増やすことができます。
また、手動で現金を貯金に回すという作業は面倒で、ついつい忘れてしまうこともあります。そのため、銀行の自動振込機能を活用すると便利です。毎月定められた日に指定した金額を自動的に貯金口座に振り込む設定にすれば、貯金を忘れることなく、効率的にお金を貯めていくことができます。
③節税をする
節税をすると、支払う税金が安くなるため、結果的にお金を貯めることにつながります。経費や所得控除など確定申告の際に所得をなるべくおさえられるように工夫をしていきましょう。
経費として計上できるものには以下のようなものがあります。
・生命保険料控除
・社会保険料控除 etc…
・生命保険料控除
・社会保険料控除
・etc……
こちらも利用できるものはなるべく利用すると、所得をおさえることができ、節税につながります。独立前にある程度調べておくようにしましょう。
④資産運用を始める
フリーランスとして働き始めたら、貯金だけでなく、資産運用も考えてみると良いでしょう。銀行口座にお金をただ預けておくだけでは、お金はほとんど増えません。
資産運用を少しずつ始めることで、貯金だけではなく、お金をさらに増やしていくことが可能になります。資産運用をする際の注意点としては、短期的な利益を追い求めることは避けましょう。短期的には大きなリターンを期待できない投資でも、長期的に保有することで利益を得られる可能性が高まります。
また、つみたてNISAやiDecoのような節税対策もあるので、こうした手段を活用しながら少額から資産運用を始めてみてください。ただし、資産運用はリスクも伴いますので、生活を圧迫しない範囲で行うように注意しましょう。
フリーランスになる前に準備しておきたいお金以外のこと
フリーランスになる前に準備しておきたいことはお金以外のことでもいくつかあります。ここでは代表的な3つのものを紹介します。
①引越しと事務所は契約をしておく
②相談できるフリーランス仲間を作っておく
それぞれ見ていきましょう。
①引越しと事務所は契約をしておく
フリーランスとして独立する前に、住居やオフィスの契約を完了させておくことをお勧めします。フリーランスに転身すると、社会的な信用証明の手段が従業員時代よりも限られるため、賃貸物件の審査に不合格になるリスクが高まります。
特に、独立直後で確定申告書などの資料がまだない場合、賃貸物件を借りることができない状況に陥る可能性があります。そのため、まだ従業員である間に、移転先やオフィスなどの契約を完了させておくことが安全です。
同様に、クレジットカードなどの審査もフリーランスになったばかりの時期には通りにくくなるため、従業員の間に申し込んでおくと良いでしょう。
②相談できるフリーランス仲間を作っておく
フリーランスとしての道を歩む上で、相談できる仲間を持つことは重要です。その仲間とは、同じ時期にフリーランスになる人ではなく、既に数年間フリーランスとして活動している先輩のような人物が理想的です。
フリーランスとして数年間活動している人なら、「自分も同じ経験をしたが、こうやって乗り越えた」という実体験に基づいたアドバイスを提供してくれるでしょう。可能であれば、同じ業界の人物とつながると、より具体的な話ができます。
フリーランスになったばかりの頃は、仕事の獲得方法、開業手続きの進め方、税金の扱い方など、分からないことが多いはずです。そのため、身近に相談できる相手を見つけておくことをお勧めします。
フリーランスでお金について勉強をする3つの方法
ここからはフリーランスでお金について勉強をする方法をお伝えしていきます。
①ファイナンシャルプランナーに相談
②スクールに通う
③本を読む
ここでは、勉強の仕方を3つ見てみましょう。
ファイナンシャルプランナーに相談
ファイナンシャルプランナーとは、お金に関する専門家のことを指します。彼らはあなたの資産やライフスタイルを考慮に入れ、どのように生活すべきかアドバイスを提供します。
ファイナンシャルプランナーに相談する利点は、個々の状況に合わせた資産の増やし方を教えてもらえることです。学校などでは一般的な知識を多くの人に教えるため、自分に合わない内容を学ぶこともあります。
しかし、ファイナンシャルプランナーは個々の状況に合わせたアドバイスを提供しますので、自分に最適な資産の増やし方を理解することができます。実際に行動を起こしながら、その結果に基づいて具体的なアドバイスを受けることができるため、知識を学ぶよりも実践を通じて学びたい人には特におすすめです。
ただし、ファイナンシャルプランナーにはそれぞれ得意な分野がありますので、フリーランスやあなたの業種に詳しい人に相談することをお勧めします。
スクールに通う
お金についての学習を深めるために、専門のスクールに通うという選択肢もあります。そこでは、お金に関する基本的な知識や株式投資、投資信託などを専門的に学ぶことが可能です。
スクールに通う利点は、お金に関する知識を体系的にプロから学べることです。多くの生徒を指導してきた実績のあるスクールなら、初心者であっても理解できるように教えてもらえるでしょう。
さらに、同じスクールに通う仲間を作ることも大きなメリットです。仲間がいれば、一人では得られない情報を共有する機会も増えます。
一人で静かに学ぶよりも、他の人と情報を交換しながら学びたい人にとっては、スクールへの参加も検討する価値があります。
本を読む
通勤時間などの隙間時間を利用して、本を読むのも一つの良い方法です。節税対策や資産運用に関する本は数多く出版されていますので、必要なものや興味のあるものから学んでみてください。
本を読むことのメリットは、それほど多くの費用を必要とせず、自分の興味のあるテーマから学べる点です。ただし、読むだけで満足せず、得た知識を実際の行動に移すことが重要です。そうしないと、知識だけが増えて実践力が伴わない、いわゆる「頭でっかち」な状態になってしまう可能性があります。
まとめ
①必要な収入と支出を把握しておく
②貯金を半年〜1年間生活できるぐらいしておく
③保険や年金に関する知識をある程度身につけておく
④確定申告に関する知識をある程度身につけておく
フリーランスとして活動するためには、お金に関する準備をしっかりと行う必要があります。会社員時代のように、会社があなたを保護することはなく、自分自身で仕事や財務管理を行わなければなりません。
フリーランスになってから何とかなるだろうと考えていると、多くの困難に直面する可能性があります。独立する前に準備できることは全て準備しておき、フリーランスとして活動を始めたら、仕事に集中できるようにしましょう。
また、フリーランスのメリットの一つは、お金を自由に増やすことができる点です。資産運用など、お金を増やす方法を学び、それを実践するように心掛けましょう。
フリーランスのエンジニアを目指すならテックビズに相談!
テックビズでは、「フリーランスエンジニアになりたい」「フリーランスエンジニアに今のスキルでなれるのか」「実際に案件を紹介してほしい」などのお悩みに対してキャリア面談を行なっております。
テックビズでは、ただ案件を紹介するだけでなく、キャリア面談をし、最適な案件をご紹介できるので、「平均年収720万円」「稼働継続率97%超」という実績を出しております。
フリーランスエンジニアに興味がある人は、ぜひテックビズのキャリア面談を活用してみてください。